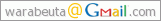うた
1. おうちの じょちゅうさんは おしゃれで こまります こまります
2. だいどこ そうじに なみだを ポーロポロ ポーロポロ
3. おとした なみだを たもとで ぬぐいましょ ぬぐいましょ
4. ぬぐった たもとを たらいで ごーしごし ごーしごし
5. あらった たもとを しっかり しぼりましょ しぼりましょ
6. しぼった たもとを おさおに ほーしましょ ほーしましょ
7. ほーした たもとを たたみで たたみましょ たたみましょ
8. たたんだ たもとを タンスに しまいましょ しまいましょ
9. しまった たもとを ネズミが ガーリガリ ガーリガリ
10.かじった たもとを ボロやに うーりましょ うーりましょ
11.うーった おかねで おそばを つーるつる つーるつる
あそび
しぐさあそびです。(セッセセあそび)
二人手をつなぎ、真向かいに座ります。手をつなぎ腕を真ん中から外側へと2回開閉した後に1〜11までの しぐさをします。
1.頬に両手を添える。 2.涙が頬を落ちる。3.涙をたもとでふく。4.洗濯する。5.たもとをしぼる。6.竿に干す。7.畳でたたむ。8.タンスにしまう。9.ネズミがかじる。10.売る。11.お蕎麦を食べる。
きろく
長崎の佐々町の池田長子さんに伝承していただいたうたです。
今となっては、女中さんということばもなくなってしまいました。女中さんとは、昔、よその家に雇われて住み込みで家事の手伝いなどをする女の人のことです。現在のお手伝いさんとかハウスキーパーにあたるでしょうか。
たもととは、着物の袖のことです。長崎にもボロ屋さんが半世紀前まではいて庶民はリヤカーという手押しの鉄パイプでできた二輪の荷車の古物を買っていたのです。
池田さんは、何でもお古のものしか使ったことはなく、物が無い時代だったそうです。
このうたは11番まで物語のように長くふりがついていますので、親子で手をつないでゆったりとあそぶようにしましょう。
(2004.4.5&2007.4.11 長崎県北松浦郡佐々町にて取材)
うた
チュチ チュチ チュチナ ボーロン ボーロン ボーロンナ
タングィ タングィ タングィ バー
しぐさあそびです。
「チュチ チュチ チュチナ」で手拍子4回
「ぼーろん ぼーろん ぼーろんな」で手のひらをひとさし指で3回丸くなぞる。
「たんぐぃ たんぐぃ」で軽くゲンコツをつくった腕を胸の前で2回まわし「バー」で手のひらを開く。
きろく
このうたは、波佐見町の吉川さんから伝承していただいたうたです。
あかちゃんにしてあげるうたは、節もですが動きもシンプルなのが一番よいと思います。
手拍子の音、うたうお母さんの声はあかちゃんにとってかけがえのない音楽です。
どんな歌手の美しい歌声、CDよりも身近ですべてをゆだねている人のうたや語りかけは特別なものと感じてうたいましょう。
お母さんが歌うと、あかちゃんはニコニコします。そしてお母さんはその表情がうれしくてまたうたうというお互の楽しいつながりが回り始めていき、喜びになっていくでしょう。
(2006年12月9日 長崎県東彼杵郡波佐見町にて取材。)
うた
みみずが さんびき はいよった あさめし ひるめし ばんのめしあめが ざーざー ふってきて あられが ぽつぽつ ふってきて
ゆきが こんこん ふってきて あっというまに たこにゅうどう
絵描きうたです。
うたの最後にタコになるように順をおって描いていきます。
1)「みみずが〜」でタコのおでこの部分として波線を3本描きます。
2)その下に「朝飯」で左に丸目、「昼飯」で右に丸目、「晩の飯」で
口を丸二重にして内丸は塗りつぶします。
3)「雨が〜」で足を数本かき「あられ〜雪〜ふってきて」は
足に点々をつけます。
4)「あっというまに〜」でいっきにタコの顔のように大丸を描きます。
きろく
このうたは、波佐見町在住で、幼い時に大村市で歌って育ち中国の大連でよくあそんだと言われる今里妙子さんに教えて頂きました。
波佐見町では他に、「みみずが三匹おりました。団子が3つありました。
雨がざーざーふりました。霰がぽつぽつふりました。大きな傘かぶったタコ入道」
と丁寧なことばになっていたそうです。
昔は、土の上に棒などで大きく絵描きながらうたってあそんでいました。
しかし残念ながら、今は土はなくなり、アスファルト道路では車が多くて
とても危険で絵描きうたなどかけません。
紙の上で書いてあそびましょう。
幼い子どもには大人が描いてみせ、2、3歳位になってなぐり書きするように
なったら大人が手を添えて一緒に描くのがよいと思います。
ことばと描き方が同じになるようリズムにのって描きましょう。
(2007年2月9日 波佐見町にて取材)
うた
にしーんたけ かぜーんふけ にしーんたけ かぜーんふけ・・・・しぐさあそびです。 布を風に見立てて振りながらうたう。
きろく
長崎県東彼杵郡波佐見町の渡辺満さんに凧揚げのうたを教えてもらいました。波佐見町で風をよぶうたとしてうたっていたそうです。
ハタ揚げには風はかかせないものです。
西の方の山に向かって大声で叫んでいたのかもしれませんね。
”あっかとばい”では春風をよびこむように薄い布であそんでいます。
長崎市では、唐八景で春に行われるハタ揚げなどの時に
風をよぶうたとして同じような「稲佐ん山から」No.11、No.37 があります。
風よびうたの波佐見版ということでしょう。
(2007年2月9日 波佐見町にて取材)
うた
たけのこいっぽん おくれ まだめは でないよたけのこにほん おくれ もうすぐ でるよ
たけのこさんぼん おくれ もうめは でたよ
うしろのほうから ひいてくれ
引き抜きあそびです。
鬼と竹の子に分かれます。 鬼が「たけのこ一本おくれ」とうたいだすと
最初の竹の子は「まだ〜」と応えて木や柱につかまります。
次の竹の子も順々に「もう〜」でつながって行きます。
最後に、みんなで「うしろのほうから〜」をうたい終えると
鬼は最後尾の竹の子を引き抜きます。
途中で切れた竹の子が次の鬼になります。
きろく
問答のある引き抜きあそびです。竹の子は腰に手をまわしてつながっていくと切れないのですが
腰が苦手な子は肩を持つことなります。
するとそこから切れてしまうようです。
手をつなぐ、腰でつながる、肩でつながる
いずれにせよ子ども同士がじかに触れる結びつきで
ワアーワアーいいながらあそべるのは大切だと思います。
この節と似ている歌で「ほうずきばあさん」があります。
これは、ほうずきが竹の子にかわってうたい
最後の節が少しちがうだけです。
ロシア民話の絵本の「おおきなかぶ」(A・トルストイ作)に
通じるものがあります。
(参考資料: 佐賀 長崎のわらべ歌 柳原書店)
うた
がんがんじみゃ ふねきゃあぎゃ ふねはかわでな うまこうて
うまはどこへんに つなでたな さんぼんまつの きのしたに
ないどんば くれて つなでたな きょねんのあわがらと
ことしのひえがらと じっぱばかり とりくれて つなで ええたとばい
あそびうた
子もりうたです。ゆっくりうたってあげます。
きろく
長崎の川棚の子もりです。
私たちは、子もりうたをうたわないで久しく、せわしない日々を過ごしています。
ゆったりとしたうたは、聴き手もうたい手をも気持ちを落ち着かせ 昔の時間や情景を思い出させるものです。
好きな子もりうたを一つは持っていたいものです。
(参考資料: 佐賀 長崎のわらべ歌 柳原書店)
うた
しおぶり こぶり しおん なきゃ ポチャリンしぐさあそびです。
ボールをゆっくりふりながらポチャリンで落として見せる。
きろく
長崎の加津佐町のわらべうたです。しおとは潮のこと、しおんなきゃとは潮の中にということです。
あかちゃんには、ボールをふりながらうたって聴かせますが
1、2歳からは、ひざ上に座らせて上下にはねさせて
ポチャリンでまたの下に落としてあそびます。
大きいボールはあかちゃんはまだ握れないのですが、このボールは手で
掴むことができ、柔らかいので形が自由になります。
ボールの中に鈴をつけたお手玉を入れ音がするようにして使っています。
(参考資料: 佐賀 長崎のわらべ歌 柳原書店)
うた
ニッポン サンケイ シナカラ ゴケジョ イタリア シベリア ドドイツ ドン
あそびかた
ジャンケンあそびです
日本は指2本を出し、さんけいは3本、支那からは4本、後家女は5本 イタリアは頬をつねり、シベリアは頬をなで、ドドイツで脇を両腕で 2回打ち最後のドンでジャンケンを出す
きろく
長崎の歴史文化協会の川崎先生に教えて頂きました。
たいそう威勢のいいジャンケンうたです。 痛いからイタリア、すべってシベリアとは言葉をうまく言い当ていて 子どもたちは大好きです。
支那とかイタリアとかシベリアなどの言葉は、オランダと同様に長崎が いろんな文化を伝え持っているからだと思います。
長崎ではこんなうたを「チャンポンのごたる」と言うのではないでしょうか。
チャンポンとは、チャンポン玉に野菜、肉、カマボコ、海鮮類の具が たくさん入ったにぎやかな食べ物です。
(2005年11月21日長崎の歴史文化協会にて取材)
うた
たばこいっぽん おとした ひろた ひろた かやせ かやせ いやよ いやよ かやさないと うしろのこを とるぞ とるなら とってみろ
あそびかた
子とろうあそびです。 鬼が親子と問答しながら最後に後ろの子を取ります。
まず鬼が、1本指をふりながら「 たばこ・・・おとした」 親子が手を打ちながら「ひろた ひろた」と順々にうたいます。
最後に親が「とってみろ」の「ろ」で両手をひろげ、子は親につながります。 鬼は最後尾の子をとろうとして親はそれを防ごうとします。
きろく
これは長崎のわらべうたです。 古くからタバコ産地である長崎ならではのうたではないでしょうか。
子とろうあそびは動きが大きいので、小学生くらいからのあそびです。
親が必死になって鬼から子を守り、子らは家族が切れないよう がんばって右往左往します。
このような外あそびは、コンクリートや室内ではなく土の上であそびたいものです。
(参考資料: 佐賀 長崎のわらべ歌 柳原書店)
うた
ねんね ねんね ねんねよ ねんね ねんね こんぼうよねんね さんせ とこさんせ あした はよう おけさんせ
ぼっちん ついて くわしゅうで ついて いやなら やいて くわしゅ
やいて いやなら たいて くわしゅ たいて いやなら なまで くわしゅ
ほうりゃ ほうりゃ ほうりゃよ おうおう おうおう おうおうよ
子もりうたです。
ゆったりと抱っこしたり、おぶったり、添い寝しながら聴かせます。
きろく
壱州とは長崎県の壱岐島のことで、ぼっちんとは餅、たいてとは煮ることです。現代は、何かと気ぜわしい、不安な時代になりました。
子どもに、子もりうたで寝かしつけることもしなくなってきましたが
母の声でゆっくりした歌を聴かせる時間は、親子ともに安心を与えると思います。
全国的な有名な子もりもありますが、できれば地元長崎の素朴な子もりうたを
うたい伝えていきたいと思っています。
(参考資料: 佐賀 長崎のわらべ歌 柳原書店)
うた
じごくごくらく えんまさんのまえで このこがいちばん よいむすめ ぎんのふねうかべて あそびましょ
じごくごくらく えんまさんのまえで このこがいちばん わるむすめ ひのやまとんで あそびなさい
じごくごくらく えんまさんのまえで このこがいちばん わるむすめ はりのやまとんで あそびなさい
あそびかた
ふりわけあそびです。
二人の子が向かい両手をつ ないだ中に一人の子が入ります。
中の子はわきを開けて、ゆすられるように体をゆらします。 うたのさいごに支えられた片方の腕から外にふり出されます。
良い娘は優しくふりだされ、悪い娘は乱暴に振り出されます。
きろく
いろんな地方に、ゆすってふりわけるあそびはあります。
このうたは、長崎の五島(岐宿町)に伝わるわらべうたですが、 京都は、類歌で問答が入っているうたであそんでいたようです。
昔は、地獄とか極楽とかはっきりとした善、悪の基準がことばでうたわれ あそばれていたんですね。
”あっかとばい”では2、3歳から振り分ける時に良い子は、親が手車に乗せて やさしくゆらします。
悪い子の時は、子どもの両手を持って飛び続けさせるあそびにしています。
(参考資料: 佐賀 長崎のわらべ歌 柳原書店
うた
オガドンナ ドンナ ヤッパリ コウコウ オガドンナ ドンナ ヤッパリ コウコウ・・・
あそびかた
二人であやとりのひも交差させ引きながらうたう。
きろく
長崎のわらべうたです。
めずらしいわらべうたを長崎歴史文化協会の川崎先生に教えてもらいました。
昔、木挽きの人が大鋸(おが)という鋸(のこぎり)で木を切っていました。 それで、大鋸屑(おがくず)をたくさんで出す人のことを“おがどん”と言って いたそうです。
このあそびは鋸(のこぎり)を使い木の両端から引き合い切っているさまを子どもが見て おもしろかったのでしょう。
それで、ひもをふたりで交差させて引き合うしぐさにしてうたって あそんだのでしょう。
あやとりは「はしご」や「ほうき」などをあそんだものでしたが 二人であやとりをしてひもを引き合うあそびは珍しいと思います。
“あっかとばい”では、あやとりをダイナミックにロープを使って体で引きあう あそびにもしています。 No.62
(2006年2月17日 長崎歴史文化協会にて取材)
うた
町でまんじゅう 買(こ)うて 日見で火もろうて 矢上でやいて古賀でこんがらかして 久山でうち食(く)うた
あそびかた
先頭の子が旗を持ち、数人の子どもたちと手をつなぎうたいながらうねり歩く。
うたい終えたら頭の子はしっぽ(最後尾) にまわり、つぎの子が先導してあそぶ。
きろく
長崎の人々になじみのあるわらべうたです。もともと羽根突きや手まり歌としてあそばれてきました。
歌詞が、それぞれの地名に合わせてうたわれています。
”あっかとばい”では今年2006年も五月四日に、うたにそって旧長崎街道を
探索する「わらべうた親子探検ツアー」を行いました。
「町で・・・」の起点の馬町から、いざ出発。
新大工町のシーボルト通りで饅頭(まんじゅう)を買い、日見峠越え。
峠で饅頭を食べて昔の人の通った足跡を探検しました。
次に、バスを乗り継ぎ矢上、古賀の藤棚、旧本田邸、終点の諫早市久山町の
饅頭店までの行程でした。 帰路は汽車に乗り長崎へ。
今は江戸時代の徒歩からすると、車であっという間のスピードで峠を越さず
トンネルを通過できます。
トンネルなどない時代の峠越えや、関所や旧農家の生活場を探検することで、
子どもたちは昔の人たちの時間と空間を感じることができました。
それに、一日に四軒の店の饅頭の味くらべは、手ごろな値段で買える饅頭の
おいしさ多様さに感動した面白いツアーでした。
長崎はほかの地より饅頭店がたくさんあります。
これは、日本で初めてオランダ船によって砂糖がもたらされた土地柄だったからでしょう。
カステラなどのお菓子の文化が開いた長崎の町ならではのうたではないでしょうか。
(2005年6月11日長崎新聞 掲載)
うた
つん つん つがれ やまん たの いしの ごと つんと つがれ一人で棒を突きながら歩き、うたい終えたら棒を後続のわたしていく。
終えたら列のしっぽについて歩くあそび。
きろく
長崎の外海、出津のわらべうたです。石を二つに割って、つばをつけて両方をたたき、つぎ合わせて相手の石と
突き当てて落としあう時にうたうとあります。
石であそんだ時ですから、男の子が好きな外あそびだったのでしょう。
”あっかとばい”では、室内ですので 2、3歳から重めの太い棒を突きながら歩きます。
初めは、おかあさんに手をつないでもらわないと歩けなかった子どもが、
だんだんにひとりで棒を持って歩くのが好きになっていきます。
このうたや棒がりっぱなおもちゃの役を担っています。
(参考資料: 佐賀 長崎のわらべ歌 柳原書店)
うた
ななくさ なずな とうどの とりが わたらぬ さきにおままごとあそびの中でします。
包丁で七草を切るようにしぐさをしながらうたいます。
きろく
毎年、一月七日に長崎の諏訪神社ではこのうたをうたいながら七草を刻んでいます。朝から七草粥のふるまいが行われ一年の無病息災を祈ります。
”あっかとばい”ではこの時期もですが、ままごとあそびにかかせないうたとして
年中あそんでいます。
ままごとあそびで重箱にいろんな料理をつくってお客さんうをもてなします。
お客さんごっこは、お互いのあいさつなどもあって、もてなしの気配りなど
大人たちの話し方や姿に変身するので子どもは面白いらしく好きです。
社会性のあるあそびですね。