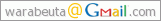うた
きんきんやんぼ やどかすな めしゃさんばいも うちくうて れいもいわずに はっていった
あそびかた
みかんの皮をむき、内皮もむいて指の先に帽子状にかぶせて その指を、動かしながらうたって食べる
きろく
長崎のわらべうたを長崎歴史文化協会の川崎先生に教えてもらいました。
冬に炬燵を囲んでみかんを食べる時、うたってあそんでいたそうです。はっていった(去って行った 長崎弁)
みかんの皮は昔は厚かったので内皮もむいて食べていたそうです。 今のは、品種改良が進んで甘く内皮も薄く食べやすくなってきて、 食べ方も変わってきたと教えていただきました。
みかん帽子を指にかぶせるのはおもしろいですね。 昔は、素朴なみかんでもあそびうたにしていたんですね。
(2005年11月21日長崎歴史文化協会にて取材)
うた
せんぶは 四枚の はねもっとる あしゃ 六本 とべとべ
あそびかた
竹とんぼを遠くに飛ばす
子どものお腹に大人の両足をあて、子どものからだをピンとさせる→高くあげ、足乗り飛行機のように上下させる
きろく
せんぶとはトンボの方言で、長崎の加津佐町では「せんぶ」、長崎市では「へんぶ」と 言われていたそうです。 「あしゃ」とは足のことです。
夏の終わりに、たくさん飛んでいるトンボを追いかけたりとったりした時の あそびうたでしょう。
近ごろは、子どもも忙しくなってきて外に出て野原や、夕方のあかねの雲 を見ながらトンボを追う姿が見られなくなりました。
子どものころ、ボ〜ッと雲の動いていくのや赤く染まる夕暮れ見たり 虫を観たり、触ったりしている時間を大切にしてあげましょう。
(参考資料: 佐賀 長崎のわらべ歌 柳原書店)
うた
1・ともさん ともさん花つみゆこや お手てつないで かご下げて
2・つんだ花々 小束になして 御母(みはは)マリアにささげましょう
3・花は我(われ)らの お手本様よ 人の心のいましめよ
4・ユリは潔白 ボタンは愛よ 派手な桜は信徳よ
5・憎しうらめし 山おろし風 咲ける桜を吹き散らす
6・咲ける花さん いくらもあれど 実る花さんいくらです
7・友よ我らも この世の花よ 徳のみのりに うまれきた
8・いかに嵐の 吹きすさぶとも 心引きしめ 気を強め
9・神の御園(みその)に 楽しむまでは しゃばの嵐に 散るまいぞ
あかちゃんをひざの上に乗せ 手を振ってあげながらうたってあげる。
また、子どもたちで輪になり 手をつなぎ、右回りや輪を縮めたり広げたり 手をかざして踊る。
きろく
長崎新聞連載の最終回となりました。
外海のド・ロ神父記念館のシスター橋口さんに教えてもらった、人の生きていく道しるべを 示すわらべうたです。
外海ではあかちゃんをひざの上に乗せ、手を振ってあげながらうたってあげていたそうです。
長崎は仏教やキリスト教が、その時代の権力に翻弄(ほんろう)され迫害された歴史があります。 その中にあって、他県にないカトリックの教えを、わらべうたの節でうたっています。
歌詞が外海の美しい風景、マリア像のある教会の風土にふさわしく、この世が徳(善の世)であること。 その徳の実りに生まれてきた私たち花は、つらいことにめげず、それぞれ心引きしめ しっかり生きましょう、と。
わらべうたは古く、もうなくなってしまったと思われる方が多いかと思います。 つい二十年くらい前まで子どもたちは、その地の風土、生活、社会状況を映しながら わらべうたやあそびをしていました。
しかし、最近は通りで友達とあそぶより一人ゲームの時代です。 心配なのは子どもの成長に、人とつながるという経験が少なくなること。
わらべうたは人とつながることでしかあそべない貴重な子どもの文化だと思います。 長崎のわらべうた、昔の人の知恵の詰まったうたを、これからも伝え続けていきたいと思います。
(長崎新聞 2005年9月掲載 2004年10月16日 ド・ロ神父記念館にて取材)
うた
ねったか ねらん かあ と まくらに きけば よ お まくら もの ゆう にゃあ ねた と ゆうた
長崎の外海の子もりうたです。ゆっくりとうたってあげましょう。
きろく
長崎の外海の森ユキさん、山口オキさんから伝えて頂いた子もりうたです。
昔、外海の人々は貧しく生活に追われていたそうです。
子どもがぐずって寝ないと、別のうたで「ねんねした子の かわいさ みぞさ 起きて泣く子の
面(つら)憎さ 面憎い子は 茶釜に入れて 松葉おりくべて ゆで殺せ」があったそうです。
現在のように子どもに、かまっていられなかった時代をうかがわせます。
当時の子どもは、夜早く寝ないと大変なことになるぞ!という
おどかしみたいなものがあったのでしょうね。
コンビニやテレビなど無かった時代は、親も子も早寝、早起きだった事でしょう。
そんな背景があった頃のうたですので、枕がものを申すとは何とも面白い詞ですし
節も美しいと思います。
ぜひ、長崎の子もりうたとして伝えていきたいと思います。
(2004年10月16日 黒崎にて取材)
うた
ひとふた ちょうろくさん なんぼがとおよ(十)とおよが二十 二十が三十 三十が四十 四十が五十
五十が六十 六十が七十 七十が八十 八十が九十 九十が百ヨー
とこいっかん かしました
あそびかた
歌に合わせお手玉を投げ上げ、受けとったり、拾ったりする。いろんなやり方がある。
きろく
対馬のお手玉歌のご紹介です。最近はお手玉で遊ぶ光景を見かけなくなりましたが、世界のお手玉の歴史は古く
紀元前からトルコの城壁には羊のかかとの骨でお手玉遊びをしている姿が彫られているそうです。
日本では、奈良時代に中国から伝わり、それが江戸時代になって布のお手玉に変わり
俵形や座布団形になっていったようです。
昔、お手玉はみな手作りで、おばあちゃんから孫へと伝承していました。
中味は大豆やヒエ、数珠玉(じゅずだま)(河原に生える野草)など。
特に数珠玉お手玉は素朴な風合いで、 握り具合や音が最高でした。
しかし、コンクリート護岸になった現在、数珠玉はなかなか手に入らなくなりました。
また、長崎の類歌として「ひとふた/ちょうろくさん/なんぼがとうふ/とうふがにんじん/
にんじんがさんしょ/さんしょがしいたけ/しいたけがごぼう/ごぼうがろうそく/
ろうそくがしちりん/しちりんがはがま/はがまがくじら/くじらが百かんめ」
という面白い歌があります。
遊びには歌がつきものですが、これには節(ふし)が伝わってなく残念です。
私たちはこの半世紀、既製の物を安易に買うことができる一見便利な社会を手に入れた半面
家族の在り方、自然環境の大切さをおざなりにしてきました。
素朴な遊びを伝えないのは、非常に残念なことだと思います。
今こそ遊びや生活を見直す時期に来ているのではないでしょうか。
(2005年8月14日長崎新聞 掲載)
うた
らかんさんが そろたら そろそろ まわそじゃ ないかいなヨイヤサノ ヨイヤサ ヨイヤサノ ヨイヤサ …
数人で丸くなって座る。おのおの自分のしぐさを決め「ヨイヤサ」の掛け声に合わせて まず自分のしぐさをして、次に右隣の人がするしぐさをまね、次々と回していきます。
そうやってしぐさリレーを何回まわすか競う。
きろく
五島のわらべうたのご紹介です。「らかん」とは阿羅漢、仏教で最高の修行者のこと。
佐々町立図書館の末永嘉代子館長に教えてもらった「しぐさ回し」あそびは 地域の集まりの時などにあそんでいたそうです。
館長は、高校生の遠足のときに、クラスのみんなと五社神社でワイワイ笑いなが あそんだ楽しい光景が思い出されると言われました。
このあそびは、子どもから大人まで楽しめ、人数が多いほど難しくなりますが リズミカルになり面白くなっていきます。
しかし、最初コツが分からないうちはしぐさが途切れて、一回も回すことが できないでしょう。
人は最初におのおののしぐさを頭で覚えてしまおうとしがちです。
これが失敗のもと。
しぐさを覚えるのではなく、ただ隣の子のしぐさを流していけば スムーズに回りだします。
そうなるとスピードも速くなり、全員が「ヨイヤサ」の掛け声で一体となります。
まさに、神輿(みこし)を担ぐような感じです。
わらべうたは、あかちゃんへの語りかけうたや顔あそびに始まります。
一人あそびから段々にあそび仲間が増え、手をつなぎ、声を合わせ歩いたり 追いかけっこしたりなど、人と人の触れ合いであそびが広がっていくのです。
子どもがコミュニケーションをはぐくむのに欠かせないあそびだと思います。
(長崎新聞 掲載)(2004年4月5日 佐々町立図書館にて取材)
うた
1・イギリス イギリス イギリス2・日本 日本 イギリス 日本
3・上海 上海 イギリス 日本 上海
4・横浜 横浜 イギリス 日本 上海 横浜
5・五島 五島 イギリス 日本 上海 横浜 五島
6・武蔵 武蔵 イギリス 日本 上海 横浜 五島 武蔵
7・名古屋 名古屋 イギリス 日本 上海 横浜 五島 武蔵 名古屋
8・八幡 八幡 イギリス 日本 上海 横浜 五島 武蔵 名古屋 八幡
9・九州 九州 イギリス 日本 上海 横浜 五島 武蔵 名古屋 八幡 九州
10・東京 東京 イギリス 日本 上海 横浜 五島 武蔵 名古屋 八幡 九州 東京
あそびかた
1から10の数の地名を歌いながらまりをつき、歌詞の最後の言葉(イギリスのス)で
まりを足掛けしたり、片腕に片足を掛けたまままりをついたりしてあそぶ。
途中で失敗したら交代する。
きろく
昭和にはやったまりつきうたのご紹介です。このうたは主に女の子の遊びで、数に合わせて一番のイギリスから十番の
東京までの地名を反復しながらまりをついていきます。
私は、このうたで小学生のころゴムまりあそびをしました。
最後の東京までいくのは、なかなか難しかったものでした。
当時の女の子の服装はまりつきに欠かせないプリーツスカート。
最後にまりを股(また)の間にくぐらせて後ろのスカートで丸め込むのに
ちょうどよかった思いがあります。 長崎でも冬にはつららが下がり、スカートに
タイツ姿。ズボン姿やカイロはなく、しもやけをつくりながらあそんでいました。
歌詞に、一つだけ地名でない戦艦武蔵の武蔵が入っているのは、戦後の名残でしょうか。
八幡といえば、当時は八幡製鉄所が大きな会社として子ども心に印象深くあります。
わらべうたは、子どもたちがその時代背景や、風土に影響を受けて語呂の良いリズムや
音に合わせてあそんで伝承してきたものです。
ですので、大人がまず意味を考えてしまう思考のパターンを取るのではなく
直感的な言葉で自由自在にあそんでいきます。
このうたは、戦後の混沌(こんとん)とした時代が安定してきて、日本中が
東京オリンピック(昭和三十九年)を目指し急成長の渦の中だったような気がします。
うたが時代を背負っていたというのでしょうか。
(2005年5月1日長崎新聞 掲載)
うた
いなさんやまから かぜもらおう
いなさんやまから かぜもらおう
いーんま かーぜ もどー そー
たこ(ハタ)あげのうたです。 布を風に見立ててふり、もどそーで布を放ちます。
他に大布を数人で持ち、うたに合わせて上下させてその大布の 風の中をくぐりぬけてあそびます。 最後に布を放ちます。
きろく
ハタ揚げに欠かせない風を呼ぶわらべうたのご紹介です。 長崎では凧(たこ)のことを「ハタ」といいます。
今年も三日に長崎市の唐八景公園で長崎ハタ揚げ大会がありました。 強風が吹き、参加した家族連れの人たちはそれぞれのハタを揚げて競いました。
うたにあるように、稲佐山からの春風が吹き込んでハタはあっという間に 空高く揚がりまるで空中に泳ぐ魚のエイのようでした。
それをたぐって右や左にスーイスイ、まるで生き物のように縦横無尽に動かします。 そして相手のハタをビードロヨマ(ガラス粉をつけた揚げ糸)で合戦させて 切って落としていくのです。
負けたハタはふらりふらりと空中に落ち、「ヨイヤー」という掛け声が 掛けられます。
港から吹き上げる稲佐山からの風は、絶品ならぬ「絶風」。 また、近くの「愛宕ん山から風もらおう」ともうたわれていたそうで 切に風を呼びたい気持ちの表れたうたでしょう。
そもそも、この祭りは長崎三大行事(長崎くんち、精霊流し)の一つで 江戸時代から伝わるものです。
昔は春の季節のお金持ちの道楽で、ハタ揚げを見物しながら芸者衆を呼び 酒宴を開く大人のあそびだったようです。
今ではブラスバンドの演奏や長崎検番の舞などがあり、家族連れで楽しめます。 サークル”あっかとばい”では、大きな布を風に見立ててうたってあそんでいます。
(長崎新聞 掲載)
うた
ケン パ ケン パ ケンケン パ外あそびです。
子どもの足が入る程度のまるい輪を1つ作り、縦上に2つ
次に1つ、2つ、1つ、1つ、2つと作っていきます。
輪を縦長に並べ、ことばの順々どうりにケンは片足とび
パは両足で輪の中を跳んであそびます。
次に、並んだ輪の中の1つに石を入れると、そこはとばして
跳んでいきます。
きろく
昔、私がよくあそんだ外あそびです。道路にチョークなどで輪を書き、跳んであそんでいました。
近ごろは、道路が車で危険な場所になりました。
本来は、屋外であそぶ時のわらべうたですが、広ければ体育館や
講堂などの屋内でもおもしろいと思います。
石のなげた場所によっては、ケンケンが続き、片足とびが
連続するとかなりの運動力がいります。
年長ぐらいからあそべますが、3、4歳は ケン パ だけの
短いうたにしたら良いと思います。
うた
もぐらうちゃ こんやまで もぐらうちゃ こんやまで ・・・(しばらくしてから)
こんくらいうっも てぶらにかえすは おんごもて じゃごもて

あそびかた
「もぐら打ち」の行事をまねるしぐさあそびです。
二枚の布を結んだ物や、新聞紙を丸めて藁のバットに見立てて 地面をたたきながらうたいます。
きろく
南高来郡の有明町に伝わるわらべうたのご紹介です。
同町にお住まいの松本信子さんに「もぐら打ち」の行事についてお聞きしました。
ここでは、一月十四日の日に、子どもたちが集まり町内の家々を回るそうです。農作物に害を与えるモグラを追い払い、豊作や無病息災などを願います。
訪れる家は、新婚のお嫁さんが初めてお正月を迎えた家。その家の軒下の地面をバット状にした藁(わら)を振りかざして打っていくそうです。
藁といっても一メートルくらいの竹を藁でまいて縄できびったものです。 たたいて回ると、その家主から子どもたちにお菓子が振る舞われます。
もしも、お菓子など何も振る舞ってもらえなかったときは、うたの最後に憎まれことばを言うそうです。「おんごもて」とは鬼の子をもて、「じゃごもて」とは蛇の子をもて、とも言われ何とも強烈な物言いです。
また、松浦市星鹿地区では、今年も一月六日に正月行事「もぐら打ち」が行われたそうです。
ここでは「祝いましょ 祝い餅(もち)くれたなら 末も繁盛 世も繁盛」「どーんとどっさり福の神」などという歌詞で、青竹を藁でくるんだ棒で玄関先の地面をたたいたそうです。
わらべうたのことばには、このような福を呼ぶものや、ドキッとするようなことばを大っぴらにうたうあそびが他にもたくさんあります。
いずれにせよ、子どもたちにとってみんなで大声を出して元気にうたうことはストレスがなくなり、その上お菓子までもらえる面白い行事なのです。
こういう行事は残し伝えたいものです。
(長崎新聞 掲載)(2005年1月10日 東向保育園にて取材)
うた
あっかとバイ カナキンバイ あっかとバーイ カナキンバイオランダさんから もろたとバーイバイ
あそびかた
No.1 と同じうたですが5歳位から、役交代のあそびにもできます。
一人が赤い布を持つ役になり、ほかの子どもは、その子を中心に外の輪をつくって
うたいながら時計回りに歩きます。
赤布役は布を高く持ち、外輪の内側を逆回りに歩き、うたの最後の「バーイバイ」で
すれ違いざまに赤布を外輪の子に渡していきます。
きろく
長崎に伝わるお正月のうたです。昔は「赤っとばい、のんのかばい、オランダさんから、もろたとばい」
とうたわれていたこともあります。
のんのか(美しい)と言うことばが金巾(カナキン)にいつしか変わっていったのでしょう。
金巾とは、昔舶来の赤や白の綿布で着物の裏地や、卓上ナプキンに使っていたようです。
日本は、お正月が現在の太陽暦に変わる明治六年までは、月の満ち欠けを基準とした
太陰暦(旧暦)で年中行事を行っていました。
しかし、長崎には江戸時代から太陽暦の一月一日に新年を祝う人達がいました。
人々が、オランダ人と呼でいた外国人達です。
この「おらんだ正月」には新年の宴会が開かれ、オランダ商館に出入りできた人達が
招かれました。
招かれた人はめいめい、白金巾のナプキンをひざの上に広げ、目を丸くして卓上に
次々出てくるフルコースの洋食を、お皿で頂く貴重なお正月の宴を楽しんでいたようです。
そこには、晴れ着を着た丸山の遊女や禿(かむろ・遊女に仕える少女)らのお酌に踊りと
賑やかな宴が、元旦中行われ長崎の人たちは、羨望のまなざしでオランダ人からもった物や
宴会の事を うわさした事でしょう。
このうたは、そんなオランダさんからもった赤い金巾を子ども達が見せびらかしたり
ひやかしたりしてあそんでいたころのうたでしょうか。
私は、小学校の時期に出島のオランダ商館跡地で育ちました。
このうたは、古(いにしえ)の長崎出島の歴史を深く感じさせるわらべうたです。
(2005年2月12日長崎新聞 掲載)
うた
ひふてんぼ ひかねば なんぼ たけんさきの つんまがって そのてを ひきゃれ手あそびうたです。
「ひふ〜なんぼ」まで手首を8回つかむ。「竹ん」から指先全部をつまみ
最後の「れ」でつまんだ後に、軽くひきます。
ひいた指は、飛ばしながら、最後の指まで束ねていきます。
きろく
もともとは、長崎の加津佐に伝わる鬼きめうたらしいのですが、”あっかとばい”では指あそびとしてあそんでいます。
ゆっくりとした時間に、子どもをひざに抱き一つ一つの指をつまんであげましょう。
指先をつままれるのは心地よいものでうたも1本、1本の指に語りかけるように
ゆっくりとした テンポでうたってあげましょう。
じかに体と接したうたは、子どもと親に落ち着きを与えます。
(参考資料: 佐賀 長崎のわらべ歌 柳原書店)
うた
イキナガ ショウモン ショウクラベ コウサン ノ セイ!佐世保独楽のヒモをかたく巻きます。 独楽の剣を上に向けたまま・逆持ちします。
ボウリングをするように腕をふり、独楽を前方へふり出します。
きろく
お正月の遊びとして、佐世保独楽(こま)のご紹介です。佐世保市立図書館の森山高昭館長に教えてもらった独楽の店は 繁華街の四ヶ町にほど近い所にありました。
店は、通りから急勾配の坂の上にあり、店の上には鉄道が走っていました。
さまざまな型の独楽が並ぶ店内は、まるでレトロのにぎやかなおもちゃ箱のような空間です。 ガタンガタンと列車が、天井の上を走るその時、独楽は震え、戸は揺れました。
独楽を手に取ってみると丁度、らっきょう型。驚いた事に、持ち方が、剣を上に向けて、 普通とは逆なのが特長らしい。
なるほど、翌日、図書館の館長室で森山館長は、背広姿で独楽にひもを
クルクルと素早く巻き逆つかみで、掛け声ととも独楽を振り出された。
しばらくすると独楽は、一点に止まって高速回転を始めました。
「こいば、澄むというばい。」と館長は幼い頃の少年に戻られたよう。
独楽の回転が緩くなると、すぐひもで独楽をたたかれた。
この光景は中国を旅した時、山東省の煙台の公園で見かけたのと同じでした。 公園で朝早く仕事前の大人が大勢、太極拳やジョギングをしていました。 そんな中、派手な音がピシャリ、ピシャリ。
気を取られ近づいて見ると、子どもは一人もいません。
大人の男女が円筒形の独楽を棒つきのむちでたたきながら遊んでいる音でした。 中国では独楽は、大人の遊びなのでしょうか。
昔、佐世保独楽は、唐船によって長崎に渡来してきたものらしく ケンカごまの異名もあるとのことです。
独楽の歌というよりは、気合いの入った、掛け声のわらべうたという感じがしました。
(長崎新聞 掲載)(2004年11月16日 佐世保図書館にて取材)
うた
ひい、ふう、三四の うぐいすが 梅の小枝に巣をかけて十二の卵をうみそろえ うみそろえてたつときは
一つふわどり 二つふわどり 三つみわどり 四つよわどり 五つ医者さん
六ちゃむこどん 七つなんぎのおもちゃんが コレラの病気をわずらって 石炭酸をふりかけられて
うちのおっかさんな血のなみだ 血じゃなかった紅(べん)じゃった
太郎さん 次郎さん タバコ一きんかいなされ タバコかおよりゃ寺まいり
寺はどこかと本願寺 本願寺のうしろはよいところ そのよいところにこができた
そのこが六つになったなら 金のきんちゃく さげさせて むこから学校の生徒が五人づれ
一でよいのが糸屋の娘 二でよいのが人形屋の娘 三でよいのが酒屋の娘 四でよいのが塩屋の娘
五でよいのが呉服屋の娘 呉服かたげて ヤサッサ ヤサッサ ハヤハヤ イッコ
手まりを足をかけながらではなく、つくだけの時のうたです。
まりをつくのは、四、五歳では難しいあそびです。
幼い子は、手始めに、なるだけ長い間つける様にがんばる。
それが上手くできたら、足掛け、股掛け、スカート拾い、背中のせ
などの上の技の段階がありました。
きろく
長崎の島原半島の西有馬の安達フイマさんから聞いた手まりうたです。単純につきながらうたったそうです。
複雑なつき方が難しい四、五歳のころはひたすら長くつくよう熱中したものです。
そして、足掛け、また掛け、スカート拾い、背中乗せなどの難しい技に
挑戦していくのです。
最近、まりつき遊びが少なくなったのは、あそびの時にうたうことを
無くしてしまったからでしょうか。 何かさみしい気がします。
歌の中でコレラの病気に触れているのは驚きです。
昔はコロリと言われ、江戸時代の「安政コレラ」では数万人が死亡したそうです。
明治時代にも西日本一帯で流行し、人々を震え上がらせたといいます。
そんなうたでも、とんちゃくなくうたうのが、まさに子どもの文化ですね。
このコレラの文言の入った類歌が、同じ長崎県ですが、遠く離れた離島の
新上五島町に残っています。
どのようにして、わらべうたという文化の交流が行われていたのでしょうか。
西有馬は、「手延べそうめん」の産地で知られています。
昔、ここから「そうめん船」と呼ばれた商い船が天草や五島、壱岐
対馬まで風に乗って行き来していたそうです。
その帆船は、そうめんや米、みそ、しょうゆ、酒などを積み込み
各地の庶民の生活を支えていたようです。
うたもまた、船に乗り広がったのでしょうね。
小さい船が離島に伝えた素朴な手まりうたでした。
(西日本新聞 掲載)(2004年9月19日 西有馬にて取材)
うた
ひっちょこ はっちょこ 酒屋ごご 酒屋がいやなら 嫁にやろ
たんす長持 はさみ箱 鼈甲(べっこ)の小櫛(こぐし)も十二本
長崎雪駄(せきだ)も十二足 こうして世話して やるからは 二番に帰ると 思うなよ
父(とと)さん何を 言わしゃんす 千石積んだ船さえも 万石積んだ船さえも
向こうの港が 悪いなら もとの港へ帰ります 私もそれと同じこと
向こうの亭主が 悪いなら もとの我が家へ 帰ります
あそび
子もりうたです。あかちゃんを抱っこしたり、おんぶしながら、ゆったりとうたいます。
きろく
佐世保の木原町に残る子もりうたです。
子もりうたは、あかちゃんにとってゆったりした落ち着きのある母のうたです。そのうたを聴きながら、心地よい波に揺られるように眠りに誘われて いきます。
このうたは昔、全国各地から、皿山・三川内焼を買い付けにきた人が木原町に伝えたのでしょう。「向こうの港が」とは、佐世保港を指しているのでしょうか。佐世保は明治時代の初めに、海軍の鎮守府が置かれ、 一漁村から人口が急に増えた軍港都市です。
又は、皿山の近くには、波佐見や有田などの有名な陶芸の里もあります。その陶器はヨーロッパや、中国に輸出されていた歴史があり、その港、長崎 の出島のことでしょうか。
三川内焼は、青絵の具の染め付けによる唐子絵(中国の子ども達の姿絵)で知られ、この里は平戸藩の御用窯として江戸時代から幕府や、朝廷に手厚く保護され陶芸で栄えた町でした。
その皿山で、親のいうまま、お嫁に行かねばならない娘の言い分。または、嫁いだ先の若いお嫁さんの気持ちを表している様にも思えます。
子もりうたというのは、親が子どもを寝かしつける時に、うたった「寝させうた」。昔、仕事で忙しい親に代わって、幼い妹弟を子守りし、おんぶしたまま遊んだり、学校に行っていた兄姉がうたった「あそばせうた」。子守奉公に出てきた人が子どもを背負ってうたった「子もりうた」などがあります。
どのような背景でうたわれたにしても、人の思い入れがは入ったゆったりとした子もりうたは、子どもの心に染みわたります。
(長崎新聞 掲載:参考資料: 佐賀 長崎のわらべ歌 柳原書店)