久かたぶりに長崎バイオパークへ行ってきました。
ここは、動物たちとみじかに触れられるので人気です。
ちょうどふれあいタイムで、孫と抱っこコーナーでティディをひざに上に乗せて、もこもことかわいいい。
カンガルーの殴り合いケンカも目の前で見れました。尻尾を支えにして飛び蹴りしたり、バデなケンカをするんですね。ビックリ!!
ここも、柵がなく広い敷地なのでゆったりとエサをやることができました。
普段はおとなしいらしいですよ。
カピパラに笹のエサをやったり、ミニブタを追いかけ、リスザルにちょっかいを出されたり。
さほど寒くない日でしたので、動物園を楽しめましたよ。
およそ30年ぶりの長崎バイオパークでした。
冬の晴れた空の下、鈍色(にびいろ)の家壁が佇んでいる。
長崎ココウオークの近く。教室までの道すがらに建っています。
この墨をぼかしたような壁面はずっとここに居てほしい。昭和を感じます。
いつも、パッキリとあざやかな色ばかりを好んではいませんよ。
昭和30年ごろの混沌とした街風景、出島〜中央橋までの中島川沿い。雑然としたボロ家並み。原風景です。
子どもの頃の街の姿がこの壁にある。ほっとします。
長崎の港・大波止の岸壁です。
停留中の船群 ちょうど岸壁めざして入港中の船。
空気が澄んで、空は晴れわたり遠くに稲佐山がくっきりみえます。

ぽかぽか日和のウッドデッキは、冬でなければ寝っ転がりたい気分です。
ここから眺める長崎って、やっぱしヨカバイと思います。
なにせ、この岸壁は昔あそんだエリアですから。
長崎の女神大橋からながめた長崎港です。
海のコバルトブルー ほんわかとした空色 美しい港湾です。
晴天に、この斜張橋の上からながめる景色は清々しい。

遠く稲佐山が見え、ふもとに長崎の基幹産業・三菱重工のドックがあります。
対岸の赤い船は島原ドックで海のブルーに引き立っています。
夜の女神大橋もステキですが、昼の吊り橋の白い鉄塔が凛としててかっこよかった。

女神大橋の下を船でくぐるのも、上を車で通るのも好きです。
長崎の街はせせこましいけれど、眼の前の海に開放感があります。
長崎駅前にある書道スタジオ “Start” に行ってきました。
月初めにある筆ペンの「Start感謝day」に参加です。
書道は小学校いらいの50年ぶり。ちょっとニガテですが道具なしで手軽に楽しめました。

最初は美文字を30分、次にアート文字を30分。基礎的な練習をします。
まずは、半紙でなくA4のコピー用紙に筆ペンで名前を書きます。
数回書いてから、アドバイスをうけました。
1)中心線を意識して書く。右寄りになりがちを注意しましょう。
2)田の字の空間、線の長さをを左右均一にしましょう。
3)アート書道は、強弱をつけ、常識を外してトライしましょう。
残りの1時間は好きな字の練習。お菓子ドリンク付きのおけいこでした。
筆をおろすときの集中力が気持ちよかったです。
あっという間の2時間でしたよ。
10月7日の朝8時すぎ、長崎の小江港です。
突然、パラパラと雨が降って、うっすらと虹がかかりました。
今年はじめて出会えた虹です。やさしく港をおおっていました。

でも今日は、長崎くんちの初日なのです。
虹はきれいだけれど7、8、9日のくんちの天気が気になる。雲ゆきが怪しい。
くんち桶屋町の本踊に同行するMさんたちは、今朝5時半の集合です。すでにお諏訪さんの出番が来ているはずです。
7時にババ〜ンの合図がなり、TV実況中継では、お諏訪さんは晴れていてほっとしました。私は9日に同行します。
どうぞ、後日まで良い天気でありすように!!
五節句は、日本になじみ深い行事になっています。
五節句の「節」というのは、唐時代の中国の暦法で定められた季節の変わり目のことです。暦の中で奇数の重なる日を取り出して(奇数(陽)が重なると陰になるとして、それを避けるための避邪〔ひじゃ〕の行事が行われたことから)、季節の旬の植物から生命力をもらい邪気を祓うという目的から始まりました。この中国の暦法と、日本の農耕を行う人々の風習が合わさり、定められた日に宮中で邪気を祓う宴会が催されるようになり「節句」といわれるようになったそうです。(日本文化いろは事典より)

明治からは新暦ですが、一桁の奇数月の奇数日が年に5回あって、その日が日本の五節句です。
1月7日…人日(じんじつ)の節句(七草の節句)
3月3日…上巳(じょうし)の節句(桃の節句)
5月5日…端午(たんご)の節句(菖蒲の節句)
7月7日…七夕(たなばた)の節句(笹の節句)
9月9日…重陽(ちょうよう)の節句(菊の節句・栗の節句)→長崎くんち
中国の三大節句は、春節、端午節、中秋節です。春節は、中国の旧正月→長崎ランタンフェスティバル

中秋節スタンプラリーで、東西南北の門を周って月餅をもらいました。
新地橋広場の出店で唐揚げ、海鮮サラダ、月餅も食べましたよ。
ビールも飲みたかったけれど、運転なのでアキラメでした。
夜にライトアップされた女神大橋です。
長崎湾の入り口にかかる橋は、水面から高さ65メートルでそびえています。
高い塔から斜めに張ったケーブルで吊ってある斜張橋。

世界最大級の客船ダイヤモンドプリンセス号も、この橋を通過して2012年4月に入港しました。
豪華客船でなくても、伊王島からコバルトクイーン号で橋をくぐって長崎湾に入港するのもいいですよ。
こんどは、女神大橋を歩いて通ってみようかな?
でも、高所恐怖症だからダメだろうなぁ。
やっと、夏が来ました。
長崎の茂木町の堤防から見た海は群青色(ぐんじょういろ)。
空も青く、遠くには雲仙が見わたせます。

梅雨が開けてスッキリした景色です。
う〜ん、海はいいなぁ。
大人のためのイベント・わらべうたげを開きました。
長崎の心田庵は、江戸時代からの由緒ある日本庭園と茶室です。
ゆっくりと庭を眺めつつ、七夕のわらべうたから元気をもらました。

みなさんで、江戸時代からのあそび・紋切り型もつくってみました。
紋切り型は、江戸時代、明治、大正、昭和初期まで日本の紋であそんでいたのです。ところが、戦後外国のモダンなものへと移行しました。
それが、10年ぐらい前にまた復興。その斬新で粋なあそびが流行りだしました。
6、7年前に教室で、たくさん子どもとたちあそびましたよ。

新暦の七夕の日はいつも梅雨の真っ最中で残念です。
7月7日は、ゲリラ豪雨もあり、晴れ間もありでしたが心田庵の緑が美しかった。
悪天候ながら、お越し頂きありがとうございました。
ものには、かたちと素材とがミックスされています。
日ごろ使うものの中に温もりがあるもの、機能的なもの、見た目が美しいもの、3拍子そろったのあまりないのです。
これは、心田庵の茅葺門の横入り口の取っ手です。

取っ手をにぎった時に温もりを感じました。
まるい取っ手は手にすっぽり収まり、こまかい筋目がここちよい。
扉に似合ったかたち。手肌にひびく素材。温もりがたいせつ!!
美しい意匠です。
七月七日、わらべうたげ・七夕会を心田庵でします。
茶室の空間で、どんなわらべうたが良いかと下見にいきました。
江戸時代からの日本庭園を眺め、茶室でできるなんてワクワクします。

「饅頭ツアー」でいつも訪れた本田邸とおなじ茅葺屋根は落ち着きます。
長崎に、こんなすばらしい場所があるなんて驚き、他県からもたくさん訪れる方がいるそうです。
そこを十人だけで楽しめるなど、贅沢なこと!!

茶室とわらべうたはミスマッチと思われるでしょうが、時代を越えてきたうたは、大人も充分に楽しめるものです。
子どものあそびうただけに留まるのはもったいない、もたいない。
わらべうたは、おもしろく、奥がふかいんです。
まだ若干名、申し込みできますよ。
五島でがっばているともチャンの紹介する桃です。
とても美味しそう!! すぐさま、注文。ソトノマから来ました。
とどいた桃はミゴトでしたよ。甘くみずみずしい!!

こんな桃をながめてるとホッコリなります。
五島は、たべもの、人、けしき、釣り・・よかところ。
ソトノマへも出かけてみたです。
ソトノマ facebook
〒853-0044
長崎県五島市堤町1348-1
電話番号 0959-88-9081
メールアドレス sotonoma@home.email.ne.jp
ウェブサイト http://sotonoma.wix.com/home
きくちゃん農園
〒853-0007
長崎県五島市福江町岳郷1755番地
TEL 0959-86-0561
FAX 0959-86-0561
大人のためのイベント・わらべうたげを七夕の日に開きます。
長崎の心田庵は、江戸時代からの由緒ある日本庭園と茶室です。
ゆっくりと庭を眺めつつ、七夕のわらべうたから元気をもらいましょう。
江戸時代からのあそび・紋切り型もつくってみましょう。

ーご案内ー
日時:2013年7月7日(日)午後1時半〜3時半
場所:心田庵・長崎市片淵2丁目18-18 (駐車場はありません)
会費:1700円 (入場料・紋切り型の材料・和菓子・飲み物を含む)
定員:10名 (要予約・子どもさんは参加できません)
連絡:Tel 095-846-1642 携 090-9797-3709 山田ゆかり
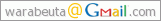

10名限定のこじんまりとした会ですので、おくつろぎ頂けます。
和菓子つきで、心田庵のわらべうたと紋切り型をおたのしみください。
大きな地図で見る
第十回「饅頭ツアー」の最後になりました。
当朝、出発前インタビューです
お疲れさまインタビューです。
お疲れさまインタビューは、峠越えをやり遂げた達成感が伺えますよ!!
誘導役の松本さん、カメラマン、ビデオマンの方々お世話になりました。
おかげさまで、楽しい「饅頭ツアー」ができました。
子どもたちもみんな元気に歩きましたよ。バンザ〜イ!!
2013年4月29日 16:30分 完