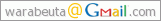2)ともさん ともさん
あそび
輪になってうたに合わせてみんなでおどる。
うた
1. ともさん ともさん はなつみゆこうや おててつないで かごさげて
2. つんだはなばな こたばになして みははマリアに ささげましょう
3. はなはわれらの おてほんさまよ ひとのこころの いましめよ
4. ゆりはけっぱく ぼたんはあいで はでなさくらは しんとくよ
5. にくしうらめし やまおろしかぜ さけるさくらを ふきちらす
6. さけるはなさん いくらもあれど みのるはなさん いくらです
7. ともよわれらも このよのはなよ とくのみのりに うまれきた
8. いかにあらしの ふきすさぶとも こころひきしめきをつよめ
9. かみのみそのに たのしむまでは しゃばのあらしに ちるまいぞ
長崎の外海のわらべうたです。
聖書の教えが西洋の節のドレミファソラシドの音階ではなく、日本の節・ミレドラソです。
他にはない長崎ならではの、わらべうたと思います。
初めて9番まであるこのわらべうたをうたうのは難しいでしょうが、
私はこういう訳がわらないものでも、まるごと身体を動かしうたっていくと
伝わると思っています。
参考にわらべうたのきろくNo.24とNo.51の「ともさん」を御覧ください。
2010年4月29日、長崎のわらべうた「町で饅頭買うて」にそって、饅頭店と旧長崎街道を
親子でたどる第七回探検ツアーをしました。
うた
町でまんじゅうこうて 日見で火もろて 矢上でやいて
古賀でこんがらかして 久山でうち食うた
きろく
晴天にめぐまれ美味しい饅頭を買いながらのツアーでした。
馬町→新大工町シーボルト通り→平井饅頭店→長崎屋→茶菓→長崎街道→蛍茶屋
→西トンネル口→日見峠→芒塚→矢上 普賢饅頭→藤棚→旧本田邸→久山 久山饅頭
馬町から出発してシーボルト通りの饅頭店で饅頭を買い、長崎街道の日見峠越えです。
峠を越えたら公園でわいわいおしゃべりしておやつを食べ、又バスに乗り矢上へ。
昼食はいつもの本田邸でそれから、わらべうたや鬼ごっこっをしました。
途中でバスに乗り遅れるハプニングもありましたが今年も面白いわらべうたツアーでした。
馬町前集合 朝9時、今年は35名です。 いざ!出発

長崎街道看板

平井饅頭店 注文のもも饅頭です。

新大工町 シーボルト通りを元気一杯に。

長崎屋 和菓子屋さんです。

茶菓 団子屋さん。

どれにしようか? 団子が人気です。

長崎街道/坂本龍馬 龍馬も1865年に日見峠を越して長崎に来ました。

お地蔵さん、無事をお願いします。

シーボルト通り 親子ですたすた元気に歩いてます。

蛍茶屋 今は電車の終点場でむかし茶屋があって蛍が飛んでいたそうです。

一の瀬橋 ここでながの別れをした石橋です。

蛍茶屋バス停 ここからは日見峠ふもとまでバスで行きます。

バス車内 スマートカードを使って。

日見峠登り口 これからが本番の峠登りです。

日見トンネル 全長864m 幅7.4m大正15年開通 。
当時のお金で総工費55万8千円、日本最大の道路トンネルでした。

峠登る。 1歳だけどがんばる天地君。

日見峠茶屋

日見峠茶屋跡 今春は寒かったのできれいな藤棚がまだありました。

日見峠越えの道

だいぶ登ったぞ。

あ!長崎の見えた。

もうすぐ、峠だ。

竹林で竹の子が、、、、

峠越えお疲れさま、おやつのもも饅頭をパクリ。

おやつも食べたし、さあ日見峠を下ろう。

芒塚へ またバスに乗り、次は矢上です。

芒塚 バスに乗ります。ぞろぞろ。

番所橋 バスから降りてまた饅頭をかうぞ。

普賢饅頭到着 予約をお願いしています。

普賢饅頭 旗が出てると饅頭有りの目印です。

饅頭、ありがとう。

藤棚 今年は蜂がいなかったので写真が写せました。

旧本田邸 昼食13時です。みんなお腹すいててモリモリ食べました。

わらべうた遊び 「町で饅頭買うて」

わらべうた遊び 「ともさん」「やまこえで かわこえで」

旧本田邸 あつまれ〜みんな、次は終点久山です。

市布バス停 最後のバスに乗り遅れる。ピーピー草で遊んでバスを待つ。

久山饅頭 おいしくて色んな饅頭がそろっているので混み合います。

久山饅頭の名物みろくです。 あんなしのふわふわ生地がおいしいんです。

久山饅頭店で解散 天気にめぐまれて気持ちのよい饅頭ツアーでした。

帰路 JR喜々津駅 JR、電車、バス、またJRと長崎をぐるり乗り物と歩きで回りました。

帰路 JR浦上駅 お疲れさま、今年もよくがんばりました。

*当日、2010年4月29日「第七回 町で饅頭買うて」の全写真サイト
*饅頭ツアーで行った店
平井餅まんじゅう
住所:長崎市新大工町2-22
TEL:095-821-7961
営業時間:8:30〜18:30
定休日:不定休
あっかとばいより:もも饅頭おいしかったです。
千寿庵 長崎屋
住所 :長崎市新大工町4-10
TEL :095-822-0543
営業時間: 9:00〜18:30
定休日 :日曜
あっかとばいより:装飾菓子、飴細工の有平糖が名物です。
茶菓 甘味処
住所 :長崎市新大工町4-10
TEL :095-822-1422
定休日: 月曜
営業時間: 10:00~19:00
あっかとばいより:みたらし団子に人気がありました。
普賢饅頭
住所:長崎市矢上町7-12
TEL :095-839-4432
定休日 :赤い旗が出ていたら饅頭あります。
あっかとばいより:お饅頭おいしかったです。
久山饅頭
住所 :諫早市久山町2487-1
TEL :0957-26-7731
定休日: 火曜
営業時間: 8:00~19:00
あっかとばいより:みろく、大福おいしかったです。
今年も長崎のわらべうた「町で饅頭買うて」にそって、饅頭店と旧長崎街道を
親子でたどる第七回探検ツアーをいたします。
5軒の饅頭店と日見峠ごえ、本田邸でのわらべうたに親子で参加しましょう。
うた
町でまんじゅうこうて 日見で火もろて 矢上でやいて
古賀でこんがらかして 久山でうち食うた
申し込み
日時: 平成22年4月29日( 祭日 )AM8:30 集合
場所: 親和銀行馬町支店前 *雨天中止
参加者: 親子15組/30人
(子どもだけの参加はできません。)弁当持参
参加費: バス代(実費)と保険100円(1名につき)
締め切り: 4月20日まで必着(多数の場合は抽選)
申し込み : 往復葉書にて
郵便番号 住所 氏名 年齢 電話番号
〒850-0047 長崎市銭座町5-12 リトム音楽教室
わらべうた”あっかとばい”山田ゆかり
参考:2003年の第一回「町で饅頭ツアー」の写真
2006年の第三回「町で饅頭買うて」
うた
オッケレー オッケレー オッケレー オッケレー
よびかけうたです。 数軒の家に見立てたもののまわりを歩きながら唱える。
きろく
これは、壱岐の芦辺町いお住いの篠崎さんと中村さんに教えて頂いたうたです。
壱岐の室町時代に開山されたという曹洞宗の本寺 龍蔵寺で昔から1月21日の朝早く行われる
お経もりの時の呼び掛けうただそうです。
朝早く青年団と子どもたちが太鼓をならして町内の家々に起きるように呼びかけながら
龍蔵寺までお経(般若心経)のお札を貰いに行っていたのだそうです。
あっかとばいでは、数軒の家に見立てた積み木のまわりを歩きながら唱えたり昼寝している
子どもを起こそうとうたっています。
(壱岐市芦辺町 2006年9月19日取材)
うた
たなわたし たなわたし しずかにわたす こがねのゆうひ おにのいないうちに おにのいないうちに
数人場合は、飲み物をこぼさないように渡しあそびにします。
多い場合は、子どもの輪の中に鬼になった子を一人いれます。
外輪の子たちはうたいながら、鬼にわからないように布や小石、木の切れ端を
まわしていき、うたが終わると鬼はその物を持っている子をあてます。
当てると交代です。
きろく
このあそびは、長崎のわらべうたです。
ハンカチ落としの一種でしょう。鬼は、外輪の子どもたちがそおっと渡していく時の
微妙な声の変化や気配を感じとって当てなければなりません。
最近は、このようなあそびもしなくなってきましたが、高度なセンサーがいるあそび
なので子どもに限らず大人も面白いと思います。
(参考資料:日本のわらべうた 社会思想社)
うた
ピーチクチャー ピーチクチャー チーチャーホーチャー ビンズルヨウニ ツーテンカラ ナーニヲモッテ オモシロイ ヤレコノ ズンズルベッコ サンノケッケ トイマンシュルベ シュクシュクションベン パーイロパーイロ ジンタン ノ!
あそびかた
ことばあそびです
早口で一息で言える様にリズムをつかみ唱える
きろく
面白いわらべうたは、何も注釈を付けたりしなくても子どもの心をグッとつかみます。
この「ピーチクチャー」を丸ごとポンと子どもの前に差し出し それを取るか否かは子ども次第です。
最初は、子どもはあっけにとられてポカンとした表情をしますが、唱えの途中「ションベン」で 思わずニヤリとし、最後は、笑って「おぼえきれ〜ん!!」でした。
しかし、すぐに唱えた子や家でお父さんやお母さんに教えてどちらが早く言えるか ゲームにしたり、さまざまな波紋が広がり出しました。
わらべうたを何十年も覚え続けているというのは、源にあるのは興味、 語呂合わせの面白さ、躍動感、それにわけがわからない?ことだと思います。
私は、子どもの時のわけのわからない?ものをそのまま持ち続けることや、興味満身の芽を 潰さないようにしたいと思います。
長崎ではわけのわからないことを「わけくちゃわからん!」と言います。
前回は、No.113
(島原市有明町2005.1.10取材)
うた
いちにとらん らんきょくってし しんがらほけっきょ きょうをの
どんがらしんがら ほけきょ
手まりうたです。ゴムまりをつきながらや足掛けしながらうたう。
きろく
五島のわらべうたのご紹介です。
このうたは、佐々町立図書館の末永嘉代子元館長に教えていただきました。
末永先生は五島、福江の小学3年生の時のまりつきをしていた時の
エピソードをお話して下さいました。
終戦の翌年で、まりつきあそびに夢中になって教室に遅刻し、先生にしかられ皆のまえで
披露しなさいと言われたそうです。
教卓の横でしぶしぶうたってまりつきをしていたら、いつの間にか興に乗ってうたい出し
教室中の皆に笑われたと楽しげに教えてくださいました。
あそびにはそれぞれの懐かしい思い出がたくさんあります。
(2004年4月5日 北松浦郡佐々町にて取材。)
うた
つ、る、は、まるまる、む、し絵かきうたです。
つは、頭 るは、耳 はは、眉 まるまるは、目
むは、鼻 しは、あごを描きます。
きろく
波佐見町の今里妙子さんに伝承していただきました。今里さんは、お孫さんに描いてあげると喜ばれるそうで
魔法みたいな絵かきうたが大好きとせがまれては
沢山書くそうです。
眉や目の位置とか、あごを長くするとかで子どもの顔になったり
おじいさんになったりと面白く顔ができあがります。
ことばと書くリズムをあわせて楽しんでみてください。
(長崎県東彼杵郡波佐見町にて 2007年2月9日取材)
うた
あっちはてっち こっちはてらんにゃ てんじんさま きらわっそうてんにもちこい うちやぶれ
あそびかた
しぐさあそびです。
おてんとさん(太陽)を指差すまねをしながらうたい、
太鼓を鳴らしながら走りまわる。
きろく
この歌は、島原市有明町の松本信子さん伝承していただいたわらべうたです。冬の寒い時期におてんとさんが恋しくて日向ぼっこをしながら
たくさん陽がほしいと歌っていたそうです。
”あっかとばい”では、冬の寒さや、内気になる気分を吹っ飛ばすように
気合いを入れてあそびます。
陽を呼び込みたい!と元気に天に向かって指差し、足踏みをし
そのあと、太鼓を鳴らして、雲を打ち破るように走り回ります。
他に、冬のわらべうたとして同類の「おしくらまんじゅう」のように
あそんでも面白いと思います。
(島原市有明町東向保育園にて 2005年1月10日取材)
うた
ピーチクチャー ピーチクチャー チーチャーホーチャー ビンズルヨウニ ツーテンカラ ナーニヲモッテ オモシロイ ヤレコノ ズンズルベッコ サンノケッケ トイマンシュルベ シュクシュクションベン パーイロパーイロ ジンタン ノ!
あそびかた
ことばあそびです
早口で一息で言える様にリズムにのって唱える
きろく
長崎の島原市の有明町の松本信子さんに教えてもらったことばあそびです。
松本さんは幼い時に、覚えていっきに言わなければいけないとお父さんから言われ、 ことばを書いた紙をトイレに持って行って覚えたそうです。
ことばは、雲雀(ヒバリ)の代弁だそうで、『巣にいる子どもに近づくな!』 という意味だそうです。
大人は、ことばの謂われはわかっても、なかなか意味が通じないと 覚えにくいのですが子どもは丸ごと覚えることができます。
小さい時に面白いことばに出会うのは、宝物を拾ったようなワクワク感があります。
子どもが育ち、学ぶのにこのワクワク感こそが一番大切と思います。
(島原市有明町東向保育園にて 2005.1.10取材)
うた
ひっちょこ はっちょこ はちのすけ はちゃあ やめえ すばかけげ
すば かけじん よめごみげ よめごは どげんどげん しおらんな
べんつけ かねつけ しおらいたざい
あそびかた
子もりうたです。
あかちゃんをゆっくり、ゆすりながらうたう。
きろく
長崎の波佐見町、渡辺満さんから伝承していただいたうたです。
渡辺さんは、おばあさんから『山に巣を作りに行った蜂の助は
巣は作らず、結婚式で花嫁さんが奇麗になる様子を見ましたよ。』という
うただと聞いたそうです。
歌詞の中にある「べん」とは口紅のこと、「かね」とはお歯黒のことだそうです。
渡辺さんは、昔、お歯黒用の金属の入った液壷にフシ(五倍子)を混ぜるため 山に取りに行っていたそうです。
お歯黒とは、昔、既婚した女性がする習慣で、今では考えられないのですが つい最近までお歯黒をされていたおばあさんがいらしたのは驚きでした。
「ひっちょこ はっちょこ はちのすけ」で始まる類歌がたくさんありますが この子もりうたは、美しい情景が見えるうただと思います。
ゆったりとうたってあげましょう。
(東彼杵郡波佐見町2007.2.9取材)
うた
コト コト ケンカシテ クスリヤサンガ トメタナカ ナカ トマラン ヒトタチャ ワラウ
オヤ タチャ シンパイ シンパイ
指あそびです。
両手を抱き合わせにする。「コト〜ケンカシテ」で小指を4回合わせる。
順次「クスリヤ〜トメタ」で薬指、「ナカ〜 トマラン」で中指
「ヒト〜 ワラウ」で人差し指、「オヤ〜 シンパイ シンパイ」で
親指を各4回づつ合わせる。
きろく
長崎の波佐見町の太田ヱツ子さんから伝承していただいたうたです。他に類歌で最後のことばが「しんぱい」でなく、「おこった」といって
角を出すしぐさのもあるようです。
私は「しんぱい、しんぱい」で最後に親指をぐるぐる回すしぐさが
ほほえましい家族のようで好きです。
まだ両手を抱き合わせたりできない、1、2歳の子にはお母さんが
手あそびにしてあげましょう。
(長崎県東彼杵郡波佐見町にて 2007.2.9取材)
うた
ほたる たるたる たんぐるまの みずは
のめば さんがれ さんがれのまねば あがれ ほたるこい ほたるこい
あっちの みずはにがいぞ にがいぞ
こっちの みずは あまいぞ あまいぞ
ひしゃく もってこい くんでのましゅ くんでのましゅ
あそびかた
自然をうたったしぐさあそびです。
柄杓(ひしゃく)を持って水を汲み飲むしぐさをします。
きろく
蛍のうたは各地にありますがこれは、長崎の多良見町のうたです。
今でも多良見町にはたくさんの蛍が飛んでいます。 ”あっかとばい”の子どもは、うたい終えたら柄杓で水を汲んだまねをして みんなに飲ませて上げます。
こどもは、柄杓の水をこぼさぬように気をつけて飲ませるのが好きです。
(参考資料: 佐賀 長崎のわらべ歌 柳原書店)
うた
チュー チュー インボリボリ タングリタングリ パー
あそびかた
しぐさあそびです。
1)寝かせたあかちゃんの両足を持ち、チュー チューは、片方の親指で もう片方の土踏まずを2回つつきます。
2)インボリボリは、両足をこする
3)タングリで大きく片足づつ回してパーで股を開く
きろく
長崎の諫早市高来町のわらべうたです。
高来町にお住まいの江頭陽子さんに伝承していただきました。 あかちゃんのおむつを替える時にうたってもらっていた わらべうただそうです。
あかちゃんがおむつを替えるのをいやがったりする時にうたいながら あやすこと。
あんよするあかちゃんの足を土踏まずをつついたり、こすったり刺戟して あげること。
足全体を大きくひねり回し開いて股関節を柔らかくしておくこと。
昔の人の子育ての知恵がきちんと入っていて、 あかちゃんに大切な運動がわらべうたなっていることは すばらしいことと思います。
(諫早市 2007年3月7日取材)
うた
なーまんじょ なーまんじょ ひーげのなーがい なーまんじょ なーまんじょ なーまんじょしぐさあそびです。
顔にひげを描くようにしぐさをしながうたう。
きろく
長崎の諫早市のわらべうたです。なあーんじょとは、鯰(なまず)のことです。
諫早にお住まいの藤山俊子さんに伝承していただいたうたです。
藤山さんのお父さんが、お孫さんの顔に何かひげのような汚れが
付いていたり、ひげに特徴のある人がいたりすると、からかい気味に
うたってあげていたそうです。
このようにわらべうたは、おじいちゃん、おばあちゃんが子どもを飛び抜いて
孫に伝えていることは、ままあることです。
最近は核家族が進んでおじいちゃん達との交流が少なくなり
わらべうたは伝承されにくくなっています。
あかちゃんから幼児まで幅広く、顔に優しくひげを描くしぐさを
しながらうたってあげましょう。
(諫早市にて 2007年3月7日取材)