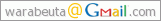うた
1. ともさん ともさん はなつみゆこうや おててつないで かごさげて
2. つんだはなばな こたばになして みははマリアに ささげましょう
3. はなはわれらの おてほんさまよ ひとのこころの いましめよ
4. ゆりはけっぱく ぼたんはあいで はでなさくらは しんとくよ
5. にくしうらめし やまおろしかぜ さけるさくらを ふきちらす
6. さけるはなさん いくらもあれど みのるはなさん いくらです
7. ともよわれらも このよのはなよ とくのみのりに うまれきた
8. いかにあらしの ふきすさぶとも こころひきしめきをつよめ
9. かみのみそのに たのしむまでは しゃばのあらしに ちるまいぞ
あそび
子どもを、ひざの上に抱っこして手を取り、振りながらあそぶ。
きろく
長崎市から車で45分ほど、広々とした五島灘を左手に見ながら西彼杵半島を ゆっくりと北上して長崎県外海町出津・黒崎地区へ。
遠藤周作 の「沈黙」の舞台となった黒崎教会を過ぎると、遺跡や歴史的建築物が集まり出津文化村 と呼ばれる一帯です。
文化村には、明治時代にこの地に功績を残したフランス人宣教師のド・ロ神父の 記念館があります。この記念館のシスターから教わったのがこのうたです。
ほほえみが印象的なシスターは、 ミサ用のオルガンの椅子に座り昔を思い出す ようにゆっくりとうたってくれました。
「この辺りでは、母親たちはみな、子どもをひざに抱っこして手を振りながら キリシタンの教えをわらべうたに託してあそんでくれたの。」とシスター は語ります。
外海町にも、禁教時代に過酷な迫害の中で、生きてきたキリシタンたちがいました。 入り組んだ地形が、キリシタンの里を守ったのでしょうか。
その貧しく質素な町にやってきたド・ロ神父は、産業や教育の発展に寄与しました。 住民たちは、今もキリシタンの教えを守り続けているのです。
子ども達はこうしたわらべうたをうたいながら、その分かち合いの精神を身に つけたのでしょう。
「旬もおいしい物が手に入ると、まず教会に持って行き、そしておとなりへ 最後に残った物を自分の家で食べたものです」と地元の人が話してくれました。
地域の助け合い精神は、今の時代にもうたい継がれているのですね。
(西日本新聞2004年12月12日掲載)
(2004年10月16日 ド・ロ神父記念館にて取材)
うた
ぞうり かんづれ かたらん もな つしのこの かみさしこうていとぶや ぶうつき ぶうつき しょうない しょうない
またごて のおのお またごての
鬼ごっこあそびです。
草履を並べ、歌の最後の「の」に当たった草履の子が鬼になって
追いかけっこしながらあそびます。
次に、捕まった子どもが草履をうたい数えます。
きろく
長崎の外海町のド・ロ神父記念館にいらしゃるシスター橋口ハセさんから教えていただいたうたです。
86歳になられるシスター橋口ハセさんが幼い時にあそばれたうたです。
その時代は、おもちゃなどではなく、身近なものであそんだと言われました。
今もシスターは、来館者にド・ロ神父が約130年前にがフランスから
取り寄せた教会オルガン(ハルモニウム)で、賛美歌をうたって聴かせておられます。
(2004年10月16日 ド・ロ神父記念館にて取材)
うた
ぎっこん ばったん ちゃんぽろりん じいにいったん おってきしゅ んべへいったん おってきしゅ ぎっこんばったん ちゃんぽろりん
両足をのばしてひざの上に子どもを乗せ、手を取りうたに合わせて 前後にはた織りをするよう紡ぐ。
または、舟こぎのようなしぐさでこぐ。
きろく
昔、長崎の外海で歌われあそばれていたていた、わらべうたです。
外海町は、かつてキリシタンの信仰が迫害を受けた時代も隠れながら 奥深い山々や、 入り組んだ海岸に守られ信仰が生き続けている地方です。
ドロ神父様の教えを守り、人と人が助け合い分かち合う精神は このうたにもうたわれています。
爺に一反、んべ(お婆さん)へ一反と歌っているのは、そのやさしさでしょう。
”あっかとばい”では、一歳のあかちゃんのグループから大切な身近な お父さん、お母さん、 兄妹、お友達の名前を入れてうたっています。
ひざの上に乗せたり、手を取り合いながらあそぶわらべうたは たくさんありますが、子どもはうたの中に 自分の知っている人の 名前が出ると思わずにっこり微笑みます。
うたが自分のものになるからでしょう。 これは大切な事で、親と体を添わせて一体となり、反物をおりながら プレゼントする人のことを想像するのです。 そして、くり返し、くり返し何人にもに織ってあげるのです。
今の時代は、物が溢れていますが素朴なうたは子どものイマジネーションを 豊かにします。
(長崎新聞 掲載:参考資料: 佐賀 長崎のわらべ歌 柳原書店)
うた
じゅうがつよー じゅう がつよ じゅうがつ いのひにゃ もちをつ く
「アー エンヤラ ヤッサ」
もちを ついても きゃくがな い 「アー エンヤラ ヤッサ」
えびすさんと だこくさんを きゃくにし て 「アー エンヤラ ヤッサ」
わたしも しょうばん いたしましょ 「アー エンヤラ ヤッサ」
あそびかた
丸太や、石、杵、わらなどに縄を巻きそれに綱を付けて 数人の子どもたちで引き、落としうたう。
きろく
このうたは、長崎の口之津のうたです。
旧暦の十月初めの「亥(い)の日」に行われる収穫祭でうたわれていました。
子どもたちはザルを持ち、各家の前で石や杵(きね)、わらなどをついて回り お餅やお菓子、お金をもらっていました。
『長崎のわらべ歌』を採譜された黒島宏泰先生のお話によると 子どもが杵を一人で引くには重過ぎるので、杵に綱を付けて両端から 数人がかりで引いて回ったそうです。
”あっかとばい”のみんなで力を出し合い引く綱は、かなりの重さの 石や丸太でも背丈ほど上げることができます。
運動場など広い広場でつくと、「とーん、とーん」と土音が響き まるで花火の音の反響のようで趣があります。
平安時代ごろ、中国から日本に伝わった祭りらしく、西日本で 行われていましたが、時代と共に風習も変わり今では あまり見られなくなりました。
(長崎新聞 掲載:参考資料: 佐賀 長崎のわらべ歌 柳原書店)
うた
いなさんやまから かぜもらおう いなさんやまから かぜもらおういーんま かーぜ もどー そーー
たこあげのうたです。
一人で布を風に見立ててふり、もどそーで布を放ちます。
他に大布を数人で持ち、うたに合わせて上下させて
その大布の風の中をくぐりぬけてあそびます。
最後に布を放ちます。
きろく
稲佐山とは長崎の港が見下ろせる山です。長崎では凧揚げは「はたあげ」といい、春に稲佐山、唐八景、
風頭山、金比羅山などで揚げます。
はたあげの時に風が止まったら風を呼び戻そうとうたったうたです。
あそびの時の大布は薄い裏地を使うと大風のかんじがでて面白いです。
(参考資料: 佐賀 長崎のわらべ歌 柳原書店)
うた
でんでらりゅうば でてくるばってん でんでられんけん
でーてこんけん こんこられんけん こられられんけん こーんこん
あそびかた
ことば、手、足あそびとしてあそべます。手あそびとしては、片手を広げ、その手のひらをもう一つの手で4つのパターンで打ちながらうたいます。
4つの手のパターンは、1)げんこつ 2)親指 3)人差し指と中指(ピースの形)4)人差し指とあかちゃん指(コンコン狐の形)です。
うたに合わせてすばやく4パターンを変えていきながら打ちます。最後のこーんこんは、1)げんこつを2回を打ちまます。段々と速くしたり、手を打つのを反対にしてもあそんでみましょう。
きろく
長崎のうたで、いろんな本や映画テレビでもとりあげられいます。
ことばの意味の取り方がそれぞれにあるようです。「ばってん」や「来られんけん」(行かれないの意味)はなかなか味わいのある長崎の方言です。
小学生の子どもは、早口うたで手と足を同時に動かしたり込み入ったあそびに工夫してあそんでいます。
うた
うさぎさんの おみみは なぜながい つきのせかいの ひめさまの
あゆみの おこえを きくがため それで ながく なったのよ 1、2、3、4・・・・
あそびかた
ペープサート、お人形などを使ってうさぎがはねるような動きでうたってあげる。
きろく
長崎の波佐見町の手まりうたとして、伝承されてきたうたです。
手まりうたは、もっとテンポも速くはずみもあったでしょう。でも最近は、手まりであそぶことが少なくなったので、私は、見て聴かせるうたにしています。
うさぎの足音を出したいので、木製のお盆をうらがえして歩みの音を響かせて。足の先に木の玉をつけています。他に、いろんな足(ビンの蓋、コルク、ボタン・・)で音を出すと又、面白いとおもいます。
このわらべうたは、月の世界の姫さまの・・とあるように情緒があります。あかちゃんにゆったりと子もりうたのようにもうたえます。
(参考資料: 佐賀 長崎のわらべ歌 柳原書店)
うた
オ ナ べ フ オ ナ べ フ ・・・・
あそびかた
「オ ナ べ フ 」と唱えながら、腕を親指と人差し指で、たぐるように腕をつかみ登る。 子どもの手首から肘までとか、手首から腕のわきしたまでつかみ登っていくきます。
丁度「オ」でつかみ終われば「お利口」、「ナ」は泣きべそ、「ベ」は勉強、女の子だったら、「べっぴん」これは美人という意味ですが 「フ」は不良と言ってあそびます。
きろく
子どもには、少しずつ腕をつかみ登る肌感がたまらないらしく、何度も占い的にしてもらいたがります。
やっぱり「おりこう」や「べっぴん」が好きです。
”あっかっとばい”(長崎のわらべうたサークル)では、今日の運勢は何かな?などと言い合ってあそんでいます。
うた
だいこん づけづけ かやりゃんせ
あそびかた
二人で向き合いてをつなぎます。
「かやりゃんせ」で手を離さずにくるりとまわり背中合わせになります。
また、「かえりゃんせ」で元の向き合わせに戻ります。
きろく
長崎の加津佐町のわらべうたです。
二人が手をはなさずにクルリと背中合あわせになるには、リズムと息をそろえなきゃ、かえりません。単純なくりかえしが楽しいあそびです。
これと同じあそびで「なべ なべ」がよく知られています。「なべ なべ」では「かえりましょ」でひっくりかえります。
(参考資料: 佐賀 長崎のわらべ歌 柳原書店)
うた
くまさん くまさん おはいんなさい くまさん くまさん りょうてをついてくまさん くまさん かたあしあげて くまさん くまさんまわれみぎ
くまさん くまさん はがきが十枚おちてます ひろってあげましょ
一枚 二枚 三枚・・・・・・十枚
長縄跳びうたです。
長縄に一人で、「くまさん くまさん おはいんなさい」から入ります。
跳びながら両手を2回地面につけ、片足とび、まわれ右、はがきが一枚から
十枚と続きます。
ひろってまでは半径まわし、一枚からは全径まわしにして跳びます。
きろく
長崎で子ども達があそんでいるわらべうたです。(2004年3月)いろんななが長縄跳びうたがありますが、跳んでいる時の動作が
かなり高度で、うたも長いので小学生ぐらいからのあそびです。
一人縄跳びにはうたがありませんが、これはみんなのうたやロープまわしの
リズム、テンポに乗れなければ最後まで跳ぶのは難しいあそびです。
わらべうたは昔のもので無くなってしまった、と思いがちですが
何気ない今日の日常の隣で、この遊びをしている情景を目にして
伝承されていることの喜びがありました。
(2004年3月 長崎市にて取材)
うた
あっかとバイ カナキンバイ あっかとバーイ カナキンバイ
オランダさんから もろたと バーイバイ
あそびかた
赤い布をふりながら、あかちゃんにうたってあげる。
他に、5.6歳位ぐらいからのあそびがあります。 あっかとばい(2) です。
まず赤い布を持つ役とそれを輪になってとりまく外輪の子どもたちがいます。 大きな外輪になった子どもたちは、時計まわりに歩きながらうたい続けます。
赤い布の役は、うたいながら外輪の内側を時計と反対にまわります。高く持った赤布を「ばあい、ばい」で外輪の子にすれちがいざまに渡し、役を交代しながらあそび続けます。
きろく
このうたは、長崎のお正月のうたです。
長崎の丸山遊女が出島のオランダさんからいろんな彩りの布をもらっていたのでしょう。
かなきん(金巾)とは、ポルトガル語のCanequim。堅くよった綿糸で目を細かく薄地に織った綿布だそうです。 着物の裏地などに使っていました。
長崎の方言で、人に得意になって見せる事を「みせびらかす」と言います。赤布をみせびらかしながら、取り合いあそぶ子どもたちの様子が想像されるうたです。
(参考資料: 佐賀 長崎のわらべ歌 柳原書店)